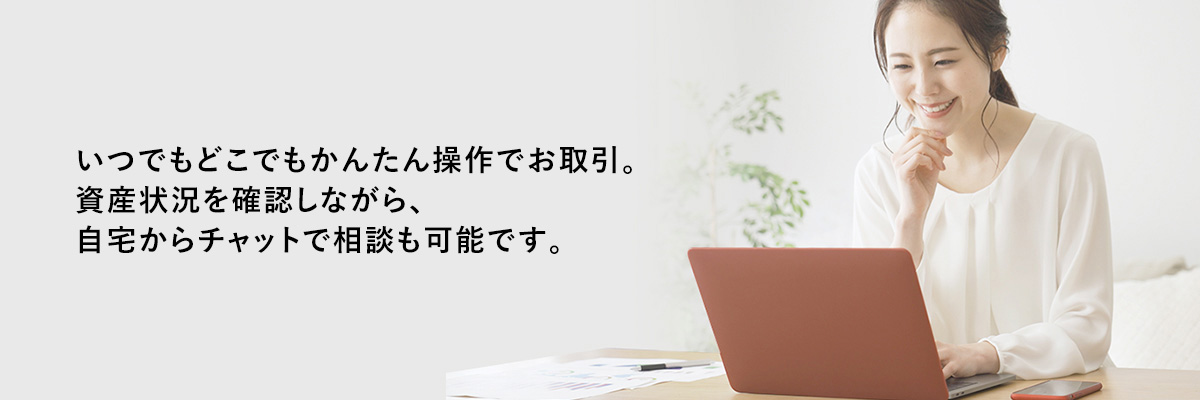ボーナス(賞与)の平均はいくら?業界や年齢別に紹介
- #ボーナス
掲載日:2023年6月19日

多くの会社員、公務員にとって、ボーナスはとても嬉しく待ち遠しい存在でしょう。とはいえ、ボーナスの有無や支給額は人それぞれです。「周りの人はどれくらい貰っているのか」と気になる方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、ボーナスの平均支給額について、業界別、年齢別、企業規模別に詳しく見ていきます。また、ボーナス支給額を上げるための工夫や、貴重なボーナスの使いみちについても併せて解説するので参考にしてください。
この記事は7分で読めます!
1. ボーナス(賞与)とは?
最初に、ボーナスがどういうものかを確認しておきましょう。ボーナスとは、毎月の固定給とは別に、労働の対価として支払われる給与のことです。「賞与」や「特別手当」という名称が使われる場合もあります。
ボーナスの支払時期は、一般的に夏(6〜8月)と冬(12月ごろ)の年2回のところが多いです。ただし、会社によっては1回のみ支給の場合や、そもそもボーナス制度を導入していない場合も少なくありません。支払額に関しては、会社の業績や個人の評価等にも左右されます。基本的には「基本給の〇ヵ月分」という形で算出されることが多いです。
会社から支給されるボーナスの種類は3つ
ボーナスは「基本給連動型賞与」「業績連動型賞与」「決算賞与」の3種類に大別されます。それぞれのボーナスの特徴は次の通りです。
- 1基本給連動型賞与
文字通り、基本給に連動して支給額が決まるボーナスです。多くの会社が採用している方法で、「基本給×支給月数」で算出します。ここでいう基本給とは、毎月支払われる給与から役職手当や残業手当、交通費などを除いた基本となる賃金のことで、総支給額ではありません。
- 2業績連動型賞与
会社の業績に応じて支給額が決まるボーナスです。業績が良ければボーナスの支給額は上がり、逆に業績が悪ければ支給額は下がります。近年は成果主義を掲げる会社が多くなっており、基本給連動型賞与ではなく、このボーナス方法を採用する会社も増えつつあるようです。
- 3決算賞与
決算前後のタイミングで支給されるボーナスです。業績が良かった年に特別に支給されるボーナスで、毎年必ず受け取れるとは限りません。支給時期は事業年度終了日の翌日から1ヵ月以内と法律で定められています。例えば、3月決算の会社なら4月末、12月決算の会社なら翌年1月末が支給期限です。
2. 【年齢別】ボーナス(賞与)の平均支給額
では、みんなはどれくらいのボーナスをもらっているのでしょうか?厚生労働省・令和4年賃金構造基本統計調査を基に、企業規模10人以上の民間企業で働く男女のボーナス平均支給額を、年齢別にまとめました。
| 年齢 | 平均支給額 |
|---|---|
| 〜19歳 | 150,700円 |
| 20〜24歳 | 382,200円 |
| 25〜29歳 | 655,500円 |
| 30〜34歳 | 799,300円 |
| 35〜39歳 | 926,100円 |
| 40〜44歳 | 1,012,800円 |
| 年齢 | 平均支給額 |
|---|---|
| 45〜49歳 | 1,081,300円 |
| 50〜54歳 | 1,159,100円 |
| 55〜59歳 | 1,155,700円 |
| 60〜64歳 | 692,000円 |
| 65〜69歳 | 350,800円 |
| 70歳〜 | 228,900円 |
- ※厚生労働省「令和4年賃金構造基本統計調査」※企業規模10人以上の民間企業で働く男女平均
この表を見ると、特に40代から50代が多くのボーナスをもらっていることが分かります。全体の傾向としては、50代前半までは年齢が上がるにつれボーナスの支給額も多くなっています。多くの会社が基本給連動型賞与を採用しており、その場合、ボーナスの支給額は基本給をベースに算出されます。
一般的に基本給は年齢や勤続年数を重ねるごとにアップする傾向があるため、それに伴ってボーナスの支給額も上がっていると考えられます。一方、50代後半からは年齢が上がるにつれ支給額は減少しています。
3. 【業界別】ボーナスの(賞与)平均支給額
次に業界ごとのボーナスの平均支給額を見てみましょう。こちらの表は、厚生労働省・毎月勤労統計調査による、令和4年の夏季ボーナスと年末ボーナスの支給状況を業界別にまとめたものです。
| 業界 | 夏季ボーナス | 年末ボーナス |
|---|---|---|
| 鉱業・採石業等 | 595,716円 | 544,459円 |
| 建設業 | 524,047円 | 498,569円 |
| 製造業 | 527,118円 | 514,074円 |
| 電気・ガス業 | 773,339円 | 805,880円 |
| 情報通信業 | 687,247円 | 662,768円 |
| 運輸業・郵便業 | 368,827円 | 390,812円 |
| 卸売業・小売業 | 357,998円 | 365,502円 |
| 金融業・保険業 | 644,728円 | 621,410円 |
| 業界 | 夏季ボーナス | 年末ボーナス |
|---|---|---|
| 不動産・物品賃貸業 | 494,650円 | 554,675円 |
| 学術研究等 | 659,687円 | 634,606円 |
| 飲食サービス業等 | 63,793円 | 67,605円 |
| 生活関連サービス等 | 157,582円 | 164,324円 |
| 教育・学習支援業 | 493,306円 | 537,569円 |
| 医療・福祉 | 275,083円 | 309,224円 |
| 複合サービス事業 | 428,876円 | 455,815円 |
| その他のサービス業 | 217,344円 | 217,774円 |
| 業界 | 夏季ボーナス | 年末ボーナス |
|---|---|---|
| 全体平均 | 389,331円 | 392,975円 |
- ※厚生労働省・毎月勤労統計調査「令和4年9月分結果速報等・≪特別集計≫令和4年夏季賞与(一人平均)」
- ※厚生労働省・毎月勤労統計調査「令和5年2月分結果速報等・≪特別集計≫令和4年年末賞与(一人平均)」
夏季・年末共に支給額が最も多い業界は、電気・ガス業でした。夏季は773,339円、年末は805,880円と、全産業平均の2倍程度のボーナスが支給されています。その他の業種で支給額が多いのは、情報通信業、金融業・保険業、学術研究等で、いずれも支給額は60万円超えと高額です。
その一方で、飲食サービス業等が最も少ない支給額となっています。夏季は63,793円、年末は67,605円で、いずれも10万円に届いていません。また、生活関連サービス等も20万円に満たない支給額で、他業界に比べると低いことが分かります。
4. 【企業規模別】ボーナス(賞与)の平均支給額
ボーナスの平均支給額は、年齢や業界によって大きく異なることが分かりましたが、企業規模(従業員数)によっても差があるのでしょうか?ここでは、企業規模別のボーナスの平均支給額をまとめました。
| 業界 | 夏季ボーナス | 年末ボーナス |
|---|---|---|
| 5〜29人 | 264,470円 | 274,651円 |
| 30〜99人 | 336,960円 | 354,645円 |
| 100〜499人 | 441,551円 | 452,892円 |
| 500人以上 | 673,602円 | 642,349円 |
- ※厚生労働省・毎月勤労統計調査「令和4年9月分結果速報等・≪特別集計≫令和4年夏季賞与(一人平均)」
- ※厚生労働省・毎月勤労統計調査「令和5年2月分結果速報等・≪特別集計≫令和4年年末賞与(一人平均)」
企業規模が大きくなるにつれ、平均支給額が増える傾向にあることが見て取れます。500人以上の大規模企業では夏季・年末共に60万円を超える平均支給額となっており、5〜29人の小規模企業と比べると2.5倍程度の差があります。
5. ボーナス支給額を上げるためにできる工夫

ボーナスについて、「支給額を今よりも上げたい」「今の支給額に不満を抱いている」という方も少なくないでしょう。そのような場合は、ボーナスの支給額を上げるために、次の方法を試してみてもいいかもしれません。
1. 仕事のやり方・進め方などを見直して成果を上げる
基本的にボーナスは個人の業績も評価されるため、支給額のアップを目指すには自分の仕事の成果を上げることが大切です。仕事のやり方・進め方などを今一度見直し、改善できる点はないかを考えてみると良いでしょう。
2. ボーナスの査定時に業績をアピールする
自分の仕事内容や成果を具体的、定量的に伝えることで、評価が高まる可能性があります。また、業務に活かせる資格を取得することで、評価が上がるケースも考えられます。自分が会社に貢献する人材であることを、いかにアピールできるかが重要です。
3. 高いボーナスが支給される(期待できる)場所への転職を検討
今いる会社よりも高いボーナス支給額が期待できる会社や業界に転職するのも一つの手です。特にボーナスの平均支給額が少ない業界で働いている方にとっては有効な選択肢となり得ます。
6. ボーナスの使いみち
ボーナスの使いみちは人それぞれですが、まとまったお金が入ったからといって散財するのは避け、計画的に利用したいものです。将来のために貯蓄や資産運用に回すのも良いでしょう。何より重要なのは、お金の管理です。お金を貯めるにも使うにも、インターネットバンキングを利用すると便利です。
東京スターダイレクトは、資産状況が一目で分かるデザイン構成になっており、お金を管理する上で便利です。貯蓄を見える化したい、ボーナスを資産運用に回してうまく活用したいと考えている方は、ご利用を検討してみてください。
7. まとめ
ボーナスの平均支給額は、年齢や業界、企業規模によって大きな差があるのが特徴です。年齢が上がるにつれ、企業規模が大きくなるにつれ、支給額は高くなる傾向があります。また、ボーナスは会社や個人の業績によって決まることが多く、工夫次第では支給額を上げることも可能です。
ボーナスの使いみちはいろいろありますが、無駄遣いせずに計画的に利用するのがお勧めです。将来を見据えて貯蓄や資産運用に回すなど、有意義に使いましょう。
以上
- ※本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。
お問い合わせ先などの情報や掲載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 - ※当行は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、記事内容の正確性、信頼性、最新情報等であることに関して保証するものではございません。