投資詐欺の手口や騙されないための注意点を解説
- #金融犯罪
- #時事
掲載日:2024年6月10日
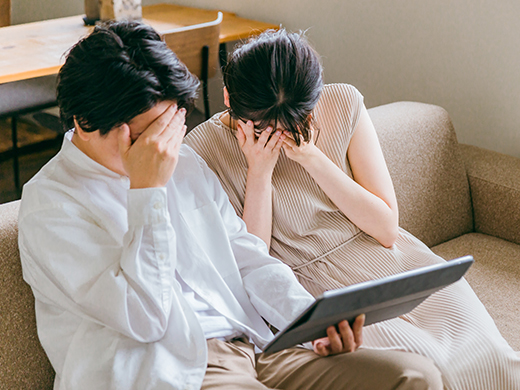
自身の資産を増やしていきたい人にとって、投資は有効な方法の1つです。しかし、そうした投資家を狙って、お金を盗み取ろうとする悪徳業者もいるため注意しなければなりません。この記事では、主な投資詐欺の手口や騙されないための注意点、怪しいと思ったときの相談先について解説します。
この記事は5分で読めます!
1. 投資詐欺の被害状況
まずは投資詐欺の被害状況について見ていきましょう。前置きとして金融庁は、預金・融資、保険、投資、貸金、暗号資産(仮想通貨)など、金融機関と消費者間のトラブルに関して、アドバイスや情報提供を行う「金融サービス利用者相談室」を用意しています。
令和4年10月1日から令和4年12月31日までの間に、金融サービス利用者相談室に対して寄せられた相談の受付状況は、以下の通りです。
| 預金・融資に関するもの | 3,982件 |
|---|---|
| 保険商品等に関するもの | 2,074件 |
| 投資商品等に関するもの | 2,245件 |
| 貸金等に関するもの | 523件 |
| 資金移動・前払式支払手段等に関するもの | 97件 |
| 暗号資産(仮想通貨)等に関するもの | 858件 |
| 金融行政一般・その他 | 1406件 |
また、別表の「詐欺的な投資勧誘に関する情報の受付状況」を見ると、投資詐欺に関する相談の受付状況は1,322件となっています。
| 被害有り | 1,048件 |
|---|---|
| 被害無(情報提供を含む) | 274件 |
| 合計 | 1,322件 |
上表の通り、投資に関係する項目である「投資商品に関するもの」は2,245件、「暗号資産(仮想通貨)等に関するもの」は858件であるため、投資に関する相談件数の約4割は投資詐欺に関する何らかの相談がされていることになります。
加えて、投資詐欺に関する相談1,322件のうち、1,048件は被害ありの報告がきていることから、相談件数の約8割は実際に投資詐欺などの被害に遭っていることがわかっています。
2. 投資詐欺の手口
ここでは、主な投資詐欺の手口を5つ紹介します。
2.1 劇場型
劇場型とは、別々の業者を装った複数の人物が口裏を合わせて、一人の消費者を騙そうとする手口です。複数の悪徳業者がそれぞれの役割を演じることから「劇場型」といわれています。
劇場型の特徴は、被害者当人から見れば、複数の人物がつながっていることが分からない点と、巧妙な演技によりリアルさが追及されている点です。これにより、詐欺銘柄の購入に対して心理的なハードルが低くなりやすく、被害に遭いやすくなります。
2.2 名義貸し型
名義貸し型は、株式や債券といった金融商品を購入する権利や名義の貸し出しを依頼し、応じた人を違法行為の当事者に仕立て上げたうえで、その被害の解決を理由に金銭を振り込ませようとする手口です。
名義貸し型は、信頼性の担保のために弁護士や公的機関といった相談機関であることを謳って騙すケースがあるため、注意しましょう。
2.3 被害回復型
被害回復型は、以前に投資詐欺に遭った人に対して被害額を取り戻せるような話を持ちかけ、金銭を騙し取ろうとする手口です。
上記の手口以外にも、「詐欺被害額を取り戻すために集団訴訟を起こすから出資金を募っている」などの手口もあります。
悪徳業者には独自のネットワークがあり、最初に騙した悪徳業者でなくても、どの人がどの被害にあったかの名簿を持っている可能性があるため注意しましょう。
2.4 SNS型投資詐欺
SNS型投資詐欺は、SNSを活用してあたかも利益が出るような表現で人をひきつけ、興味を示した人に投資を勧めて、金銭を騙し取ろうとする手口です。海外サイトに誘導して送金させようとするケースもあるため、一度送金してしまうとお金は戻ってきません。
特に見られる手口として、高級ホテルでの食事シーンやハイブランドのアイテム画像を背景に「投資が成功した。このような生活をしたい人はDMやLINEで教えます。」といったテキストを施した投稿をユーザーが見て、羨ましいことを理由に連絡を取ってしまうケースが挙げられます。
2.5 ロマンス詐欺
ロマンス詐欺は、SNSやマッチングサイトで知り合った人と非対面で複数連絡を取り、親近感や恋愛感情を抱かせた上で虚偽の投資話を持ち出し、金銭を騙し取ろうとする手口です。
なお、警察庁の広報資料によると、令和5年に都道府県警察が認知した投資詐欺のうち、SNS型投資詐欺は2,271件、ロマンス詐欺は1,575件です。被害者の年齢層は男性が50〜60代、女性は40〜50代が多くなっています。
| 認知件数 | 被害額 | |
|---|---|---|
| SNS型投資詐欺 | 2,271件 | 約277.9億円 |
| ロマンス詐欺 | 1,575件 | 約177.3億円 |
| 合計 | 3,846件 | 約455.2億円 |
3. 騙されないための注意点
投資詐欺の被害に遭わないために、適切な金融リテラシーを身に付けることが大切です。ここでは、投資詐欺に遭わないために注意すべきことについて見ていきましょう。
3.1 登録業者か確認する
幅広い投資家に金融商品の出資を勧誘できるのは、金融庁(財務局)の登録(届出)を行っている事業者に限られます。金融庁の免許・許可・登録等を受けている事業者は金融庁ホームページ「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」で確認できるため、少しでも怪しいと思ったら、こちらのサイトで確認しましょう。もし掲載されていない場合は、金融庁や警察に相談してみましょう。
また、金融庁は、無登録で金融商品取引業を行ったことで警告書を出した事業者の一覧「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」も公開しています。詐欺の疑いがある連絡がきた場合は、連絡時に会社名などの情報を聞き、一覧で名前が挙がっている事業者かどうかを確認することも大切です。
3.2 「確実」「必ず」「元本保証」等の表現に気を付ける
投資勧誘の際に、投資家の興味を引こうと「必ず儲かる」「元本保証」といった言葉を使っている場合は注意が必要です。
株式や投資信託、債券といった金融商品は、経済情勢や金利などさまざまな要素で価格が上下するため、必ず元本割れのリスクが伴います。
それゆえに、どの投資商品も100%の確率で儲けるのは不可能であることはもちろん、元本保証も存在しません。「必ず儲かる」「元本保証」という言葉を使っている業者がいる場合は、真偽は問わず悪徳業者であると断定し、関わらないようにしましょう。
3.3 「未公開株」や「私募債(しぼさい)」の取引を勧誘
一般的に「未公開株」や「私募債(しぼさい)」が、幅広い投資家に紹介されることはありません。そのため、投資商品を勧められた際にこのような金融商品を提案された場合は、詐欺を疑いましょう。
そもそも未公開株とは、会社法上で譲渡制限があり、会社の許可が下りないと譲渡できない株式のことです。また、私募債とは、特定少数の投資家に対して引受を直接的に依頼する社債のことを意味します。
いずれも購入するのが困難な金融商品であるため、これらの金融商品をネタに投資話を持ち掛けられた場合は、勧誘してきた事業者が金融庁の登録業者かを必ず確認をしてください。
3.4 金融リテラシーをつける
金融リテラシーとは、お金に関する知識や判断力のことです。近年では投資詐欺の内容も巧妙化しているうえ、現金を扱わないお金のやり取りも普及しており、金融リテラシーの必要性がますます高まっています。
金融商品に関する正しい知識があれば、悪徳業者の話に矛盾が生じていることに気付きやすくなり、投資詐欺などのトラブルに遭う可能性は少なくなります。
また、自分は金融リテラシーを身に付けていると自負している場合でも、過信からトラブルにつながる可能性もあります。そのため、過信しないことはもちろん、継続的な金融知識の習得を心がけましょう。
金融庁の金融経済教育委員会では、最低限身に付けるべき金融リテラシーとして以下の4つを挙げています。
- 家計管理:家計の赤字は解消し、黒字を確保する適切な収支管理を習慣化すること
- 生活設計:ライフプランを明確にすること
- 金融と経済の基礎知識と金融商品を選ぶスキル:金融商品の契約をするときの姿勢、適切な情報源の選び方、経済情勢に関する知識などの基本知識を身に付けること
- 外部の知見の適切な活用:不明な点は適切な情報源を活用する必要性を理解していること
東京スター銀行では、金融リテラシーを付けることに役立つ記事を多数公開しています。ぜひこちらもご覧ください。
4. 怪しいと思ったときは金融庁や警察へ相談
金融商品の勧誘を受けた際に少しでも怪しいと感じたら、金融庁や警察などに相談してみましょう。主な相談先は、以下の通りです。
| 相談先 | 主な相談内容 |
|---|---|
| 金融サービス利用者相談室 | 暗号資産(仮想通貨)を含む、金融サービスに関する相談 |
| 都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口 | 暗号資産(仮想通貨)や、インターネットを通じたサイバー事案に関する相談、通報 |
| 消費者ホットライン | 不審な電話などに関する相談 |
5. まとめ
金融庁「金融サービス利用者相談室」宛てに寄せられた投資に関する相談のうち、投資詐欺に関する相談は約4割を占めています。加えて、投資詐欺について相談した人のうち約8割の人が、実際に被害に遭っているため、日頃から細心の注意が必要でしょう。
投資詐欺から自身の資産を守るためには、金融リテラシーを身に付けることが得策です。金融リテラシーは自身の資産を守るだけでなく、増やしたいときにも役立ちます。また、投資詐欺特有の勧誘の言葉や「未公開株」「私募債」といった特定の投資商品に関する勧誘を受けた場合に迅速に対応できるよう相談先を知っておくことも肝要です。
投資は、昨今の老後2,000万円問題や実質賃金の低下といった問題に対して有効的な手段と重要視されているものの、詐欺被害と隣り合わせです。日頃からテレビやインターネット、新聞、書籍などを通じて金融リテラシーを高めるように心がけましょう。
- ※本記事に記載された情報は、最終更新日時点のものです。
お問い合わせ先などの情報や掲載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 - ※当行は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、記事内容の正確性、信頼性、最新情報等であることに関して保証するものではございません。









