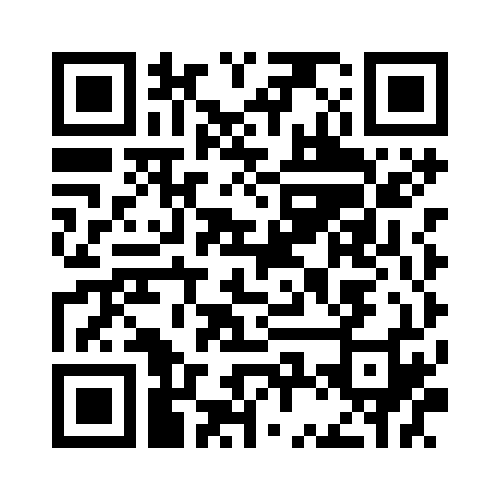投資信託に託す想いは「三者三様」
- #資産運用
- #投資信託
掲載日:2018年11月1日

定期預金であれば、利用する人の想いは「普通預金より高い金利のものを」ということに集約されると思いますが、投資信託については、購入者の想い/購入スタイルは、大きくいって以下の3つに分かれると思われます。
- 1【効率派】なるべくコストをかけず、マーケットの大きな流れに乗って、同じぐらいの収益率を目指す
- 2【醍醐味派】未来を見通す力で、他よりも儲かりそうなファンドに勝負をかける
- 3【社会的意義派】儲けるだけではなく、社会的意義を考えてこその投資
構図としては、「効率派vs.醍醐味派、それとは少し違った位置に社会的意義派が陣取る」というかたちになるでしょう。
この記事は5分で読めます!
1. 効率派vs.醍醐味派
まず、「効率派vs.醍醐味派」については、マーケット全体の潮流に乗るべく
「ある市場の値動きに連動するように設計されたファンド=インデックスファンド」
を買うべきか、より大きいリターンをねらって
「プロによって厳選された銘柄で構成されたファンド=アクティブファンド」
を買うべきか、という問いに還元できると思います。
投資する際に直面するこの問題について、プリンストン大学教授のバートン・マルキール氏は、ある見解にたどりついています。投資家のバイブルとして名高い『ウォール街のランダム・ウォーク』の著者として名を馳せたマルキール氏の意見は傾聴に値するとして、実に多くの専門家に評価されています。
それは、
「一般人ならば、インデックスファンドに投資しなさい」
というものです。かなり意訳していますが、結論としてはこうなります。
「投資理論の教えによれば、“最も効率的な投資方法”に最も近いのがインデックスファンドの購入である」、
「過去のデータを実際に見てみても、インデックスファンドの成績は平均的にはアクティブファンドを上回っている」、
「アクティブファンドを複数購入すればインデックスファンドを買ったのと大差はないし、であればコスト面でインデックスファンドの方がよい」
などなど、インデックスファンドを支持する声は数多くあります。
大きく儲かることはないけれど、マーケットの動き以上に大きく損をすることもないため、適度にリラックスして投資に臨むことができます。
とはいえ、インデックスファンドにも多数の種類があり、日本市場に連動するもの(より具体的には、日経平均に連動するものや、東証株価指数=TOPIXに連動するもの)もあれば、世界の市場に連動するものもあります。
日本の未来に対して強気か弱気か、世界全体の流れに乗るか、あるいは新興国全体に注目するかなど、インデックスファンドの購入においても、大枠での投資スタンスや未来への展望を持つ必要があり、どの地域にどの割合で投資するかなど、問いは尽きません。
一方、アクティブファンドは、ファンドマネージャーと呼ばれるプロ投資家が、どの国の、どんな業種の、どんな企業に照準を当てるか、企業の実力から考えて低い値付けがされている株式はないか、これから成長が見込める企業はないか、など、その方針を定めて比較的狭いカテゴリーに投資をしていきます。
市場平均以上に成長することを目標にしますが、逆に市場平均にも満たない成果で終わってしまうリスクもあります。
投資家の先見の明が試される投資といえますし、そのことに「投資の醍醐味」を感じる人も多いでしょう。
ここでもマルキール氏は言います。「対象が株式であれ、珍しいダイヤモンドであれ、投資がもたらすリターンは程度の差こそあれ、将来何が起こるかに依存している。そこにこそ投資の醍醐味がある」と。
たとえば「AI」「ロボット」「バイオ」「エネルギー」「環境」「宇宙」など、21世紀を賑わすであろうキーワードは数々あります。
投資の面白さを追求していくと、漠然と幅広に投資を行うのではなく、その中でも特に成長すると思われる国や成長分野を探し出す、つまりはどんな未来が待ち受けているのかを予想して、そこに投資をすることで楽しさが味わえることになります。
運用会社や販売会社側からみると、インデックスファンドはアクティブファンドに比べて投資銘柄のリサーチや商品説明にかける手間暇を少なくすることができますので、コスト面ではいわゆる信託報酬や販売手数料などの費用をおさえることができます。
また、アクティブファンドが長きに渡って好成績を収めることは難しく、その多くがインデックスファンドの成績よりも劣るという過去のデータをもって、インデックスファンドへの投資がもっとも効率的であると判断する専門家もいます。
しかし、世界には、例えばこの10年間の平均リターンが年30%を超えるという、非常に優れたパフォーマンスを上げ続けているアクティブファンド(※)があることも事実です。
(※)「USAA Precious Metals and Minerals Fund」2011年1月3日現在での、直近10年間の年平均騰落率。
効率性と収益性、いずれも魅力的です。
未来をどう予見するか、あるいは予見できないものとして平均点を目指すか、これは投資の世界では永遠のテーマといえます。
2. 社会的意義派
最後に、社会的意義派について述べましょう。
「エコロジーに力を入れている企業に投資する」
「CSR(企業の社会的責任)を重視している企業に投資する」
というのが、このカテゴリーの分かりやすい例かもしれません。
「自らの投じた資金で、どのような企業を応援するか」
「自らの投じた資金が、どのような未来を造っていくか」、
そのような意識を持って投資に臨むのが、この社会的意義派といえるでしょう。
アクティブファンドであれば、「ある特定の国や業種を応援する」というイメージを持ちやすいでしょうし、インデックスファンドであっても、「市場全体を底上げする投資」というイメージを持つこともできます。
「日本人なら日本株に投資を!」
と強く主張する人がいることも、そうしたお金の循環が生み出す経済効果を思ってのことでしょう。
人が働くことで経済は活性化しますが、お金が働くことでも同じような効果が生まれます。
皆さんの分身ともいえる大切なお金に、よりよい働き口を探してあげる。
そのような気持ちで投資を考えられるのも、この社会的意義派かもしれません。
効率的な運用と、未来を予想する醍醐味、そして社会的意義という3つの側面。
皆さんは、どのスタンスに共感されるでしょうか?
どれかひとつに絞ることができなければ、それぞれの側面から選んだ3つのファンドに分散投資するという方法も面白いかもしれません。
自らのポートフォリオの中心(コア)にインデックスファンドを据えつつ、ある部分(サテライト)では投資の醍醐味を追及するという、「コア&サテライト」と呼ばれる投資スタイルも、広く知られています。
皆さんも、自分なりのスタイルを持って、投資信託での投資を楽しんでみませんか?
- ※本記事に記載された情報は、掲載日時点のものです。
お問い合わせ先などの情報や掲載内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 - ※当行は、細心の注意を払って情報を掲載しておりますが、記事内容の正確性、信頼性、最新情報等であることに関して保証するものではございません。